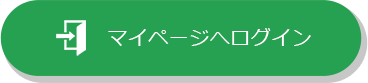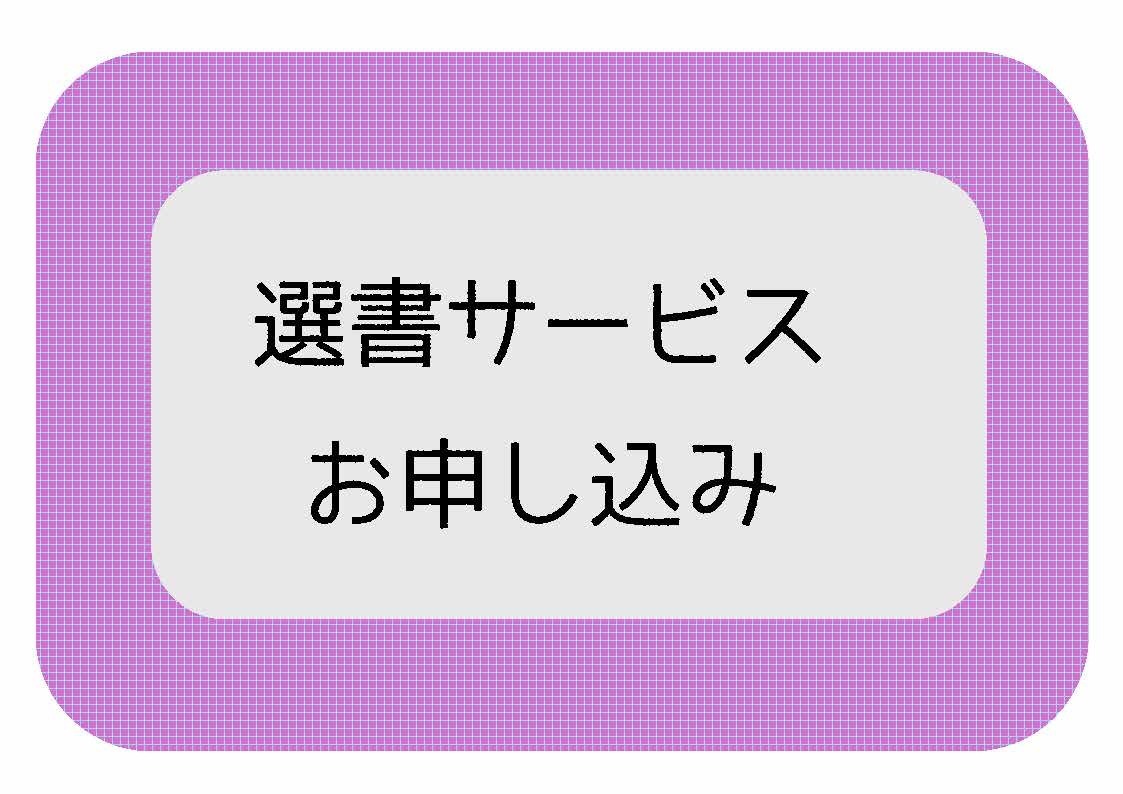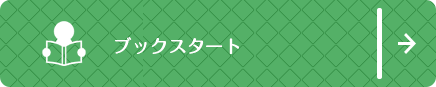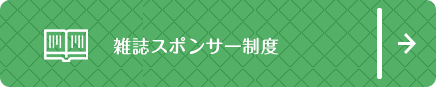相生市立図書館のスタッフが館内のPOPで紹介している本です。
なにを読もうか迷ったときの参考に、ぜひご活用ください。
探している本が見つからない場合は、お気軽にスタッフまでお尋ねください。
スタッフPOP本
『三びきのやぎのがらがらどん 』 ノルウエーの昔話 福音館書店 P
ある日、3びきの”がらがらどん”というやぎたちが、太ろうと山へむかっていました。
すると、3びきの前にトロルが現れ、道をふさいでしまいますが、一番大きいがらがらどんが、トロルをこっぱみじんにして前進します・・・。
※一日図書館員の子どもたちがおすすめする本です!
『ライト兄弟』 たかはし まもる//著 ポプラ社 28-ラ
ライト兄弟は5人兄弟。
三男のウィルバー、四男のオーヴィルは二人で自転車屋をはじめ、自転車も作っていた。
でも、二人の夢「空を飛ぶこと」をもう一度決意。どうなるのか・・・!
※一日図書館員の子どもたちがおすすめする本です!
『飼育委員はアキラめない』 小松原 宏子//著 静山社 91-コ
アキラが飼育委員になって、ニワトリとウサギを育てます。
でも、アキラには秘密があって、それは、生き物を一回も飼ったことがないことです。
おもしろいので、ぜひ読んでみてください。
※一日図書館員の子どもたちがおすすめする本です!
『引きこもり姉ちゃんのアルゴリズム推理』 井上 真偽//著 朝日新聞出版 91-イ
みんなはどれくらいお風呂に入る? ふつうは1日1回。
でも、小学6年のぼくの家の二階には「開かずの部屋」があり、その中にいるヤツは・・・。
また、部屋の前にある「クエスト依頼」それを見ていると「ウッキャアー!」!?
※一日図書館員の子どもたちがおすすめする本です!
『時間割男子 1』 一ノ瀬 三葉//著 KADOKAWA 91-イ
花丸円(はなまるまどか)という小学5年生の女の子は、勉強が超・超・超ニガテ!
大好きなママのために猛勉強してたのに、ママが死んじゃって心は真っ暗!
そんな私の前に算・国・理・社の4人の男子が!
彼らの寿命は円のテストの点数で決まる!
※一日図書館員の子どもたちがおすすめする本です!
『ふしぎ駄菓子屋銭天堂 8』 廣嶋 玲子//著 偕成社 91-ヒ
不思議なお菓子屋のお話です。
悩みを解決してくれるお菓子やおもちゃなどがあり、それを買うと望みどおりになるというお話です。
※一日図書館員の子どもたちがおすすめする本です!
『びっくり ゆうえんち』 川北 亮司//著 教育画劇 P-カ
なつきちゃんが遊園地で不思議なジェットコースターにのるお話です。
海の世界やサバンナの世界、宇宙にまで行けるすごいジェットコースターです。
かいじゅうの鼻をくすぐるってくしゃみをするところがぼくは大好きです。
※一日図書館員の子どもたちがおすすめする本です!
『盗賊会社』 星 新一//著 理論社 91-ホ
「盗賊会社」は、どろぼうごっこのおもちゃを売ったりする会社ではない。
本当のどろぼうなのだ!
しかも、社員が100人ほどいるくせに、やることは金持ちの財布をスること!
社員がわざとこけて、金持ちが気を取られているすきにスる。
主人公は、こけた社員に遅れてかけ寄る役。
他にもいろいろお話が載っているので見てみてください。
※一日図書館員の子どもたちがおすすめする本です!
『11の成功例でわかる 自分で自分の介護をする本』 小山 朝子//著 河出書房新社 369
これから先、何が起きるかわからない。
いつか、ひとりになる覚悟は必要。
本書では、ひとり暮らしを支える介護保険や自治体のサービスが紹介されています。
しかも、実例をあげながらなので、とてもわかりやすい!
現在では、高齢期の過ごし方もいろいろな選択ができるのです。
『こころのねっこ』 読売新聞生活部//監修 中央公論新社 911.5
読売新聞家庭面の「こどもの詩」55周年記念の精選集です。
子どもの視点や自由な発想から書かれた詩はすごい!
思わず笑ってしまったり、キュンとなったり、共感したり感動したり、心が動かされます。
平田俊子さんの選評も子どもの気持ちに寄り添っていてなんとも温かい。
何度も読み返し、子どもたちが愛おしくなる一冊です。
『それでも旅に出るカフェ』 近藤 史恵//著 双葉社 F-コ
店主が、あちこちを旅していろんな国のスイーツや飲み物を再現し、メニューにしている「カフェ・ルーズ」が舞台。
お客の悩みやモヤモヤ、ちょっとした事件を解決する鍵は、スイーツだったり、飲み物だったり。
おいしいモノを食べて軌道修正できたりもする。
どれもおいしそうで、聞いたことも見たこともないメニューが出てくるのが、この本の最大の魅力!
コロナ禍に入ってから長らく休業していたが、営業再開しました。
『ときどき旅に出るカフェ』の続編です。
『日比野豆腐店』 小野寺 史宜//著 徳間書店 F-オ
日比野豆腐店は、3代続く豆腐店。
コロナで店主である父親が急逝する。
店を閉めようと思った祖母、自分の仕事を辞めて店を続けようとする母親、高校生の息子、そして飼い猫の福が、それぞれの視点で家族のこと、今後の店のことを語っている。
無理せず自分を大事にしつつ家族を思いやる気持ちの奥には、温か~いモノがある。
そんな人たちが作る豆腐は、きっとおいしいに決まっている。
『1分で精神症状が学べる本304』 松崎 朝樹//著 KADOKAWA 493
「こんな症状、私だけ?」「あの人は、なんであんなことをしているの?」
本書を読めば、自分が悩んでいることに名前があるとわかるかもしれません。
精神症状を学ぶことで、あなたとは少し異なる言動を取る人がいても、
「よくあることで、何も問題はないんだ」と理解を深められるかもしれません。
本書は、明らかな精神障害によるものから、病気とは言えないが誰にでも起こり得るものまで含め、
304にも及ぶ精神症状について解説した一冊です。
『それも含めてハッピーエンドに向かってるから人生は』 過眠ちゃん//著 KADOKAWA 159
表紙の水色とピンクのイラストが、印象的ですね。
恋愛に依存して生きてきた著者の気づきや学びが、まとめられています。
恋愛だけの話かと思いきや、仕事・人間関係・自分との向き合い方についても書かれ、どんな悩みに対しても、まずは自分に、いたわりを持って行動しなければならないと教えてくれます。
読めば、心がほぐれ、少しずつ前を向いていこうという気持ちになれる1冊です。
『かずをはぐくむ』 森田 真生//著 福音館書店 599
月刊誌『母の友』に5年間にわたって連載したエッセイをまとめた1冊です。
当時0歳と3歳だったお子さんが成長する間に、日々の生活の中で「数」を育んでいく様子が綴られています。
時に、ハッとするような子どもたちの問いかけや、素直な驚き、喜びに、おとなの当たりまえが当たりまえではないと気づかされます。
いくつになっても新鮮な心を保つために、知ることや気づくことを怠ってはいけないと、優しく諭された気持ちになります。
『好きになってしまいました。』 三浦 しをん//著 大和書房 914-ミ
著者が好きなものは、お酒、食べること、旅することなどなど。
『好き』が多岐にわたっているということは、きっと心も豊かなのだろう。
日常のささいな出来事をも、おもしろおかしく感じて生きていける才能の持ち主とみた。
・・・「またアホなことをやらかしとるな」と珍奇な生物を観察する感じで、本書をお楽しみいただけたなら幸いです。・・・
とあとがきにあるが、こちらは読み進むうちに、笑ったり、驚いたり、呆れたりしながら、読後はすっかり著者のことを好きになってしまっている。
『捨てられた僕と母猫と奇跡』 船ケ山 哲//著 プレジデント社 645
アニマルセラピーというものがあるように、動物には人の心を癒す力があることが認識されています。
この本に出てくる猫は、普通の猫ですが、著者を時に励まし時に癒して、その一生を終えます。
物言わぬ猫だからこそ、人の勝手な想像で猫の心を察するのですが、ただそこに居てくれるだけでいい安心感に共感できます。
きっとあなたのペットたちもこう思っているはず・・・
『DIE WITH ZERO』 ビル・パーキンス//著 ダイヤモンド社 159
ー人生でしなければならない一番大切な仕事は、思い出作りです。最後に残るのは、結局それだけなのですから。ー
確かな将来の計画を持ち、同時に今を楽しむことも忘れない。
有名な寓話「アリとキリギリス」のキリギリスはもう少し節約すべきだし、アリはもう少し今を楽しむべきなのだと説く。
自分にとって最適な選択をするための人生の指南書。
『まっすぐだけが生き方じゃない』 リズ・マーヴィン//著 文響社 653
擬人化した樹木から生き方を学ぶ。
人間と樹木には、呼吸したり、成長したり…長い年月、環境に適応しながら生き延びているという共通点もあります。
樹木の特徴をよく表現したイラストとともに、60の生きるヒントを紹介しています。
読むと、緊張やストレスが解消され、まさに森林浴ができそうな1冊です。
『存在のすべてを』 塩田 武士//著 朝日新聞出版 F-シ
平成3年に起きた誘拐事件から30年。
未解決のその事件を調査していくうちにある写実画家の存在が浮かび上がり・・・
読み進めていくうちに被害者の男の子とその画家夫妻の関係がどんどん深まり、胸が苦しくなる状況におちいっていき、最後は号泣でした。
作者が元新聞記者ということもあり、事件に関する描写や取材していく過程などがとても分かりやすく読みやすいと思います。
『春期限定いちごタルト事件』 米澤 穂信//著 創元社 F-ヨ
小鳩君と小佐内さんは、今日も手に手をとって、清く慎ましい小市民を目指す。
それなのに、二人の前には頻繁に謎が現れる。
なぜか謎を解く必要に迫られてしまう小鳩君は、あの小市民の星をつかむことができるのか?
コメディ・タッチのライトなミステリ。
※トライやるウィークの中学生がおすすめする本です!
『君の膵臓をたべたい』 住野 よる//著 双葉社 F-ス
高校生の僕は、ある日、病院で1冊の本を拾った。
その本の名前は「共病文庫」。
それはクラスメートである山内咲良の秘密の日記で、「もう長くはない」と記されていた。
これをきっかけに、日常のない彼女と僕との日常が始まった。
だが、そんな日常もすぐに終わりをむかえることとなる・・・
※トライやるウィークの中学生がおすすめする本です!
『描きたい!!を信じる』 週刊少年ジャンプ編集部//著 集英社 726
週刊少年ジャンプが教えるマンガの描き方を紹介!!
作品を作る時、誰しもが抱える問題も解決!
内にはあの「僕のヒーローアカデミア」原作者の堀越先生や「ONE PIECE]原作者の尾田先生のアンケートなども!
※トライやるウィークの中学生がおすすめする本です!
『やっぱり犬がほしい』 スギヤマ カナヨ//著 アリス館 91-ス
ぼくは犬が大好きで、近所の犬たちも仲良し。
シールや切手、クッキーの缶も集めていて、お気に入りの犬はパルという。
パルは散歩ができないし、呼んでもこない、何をしてもこない。
だが、お父さんに犬の寿命は15年と聞いて、死んだ時のことを想像してパルを抱きしめて泣いた。
※トライやるウィークの中学生がおすすめする本です!
『小説ブルーピリオド』 時海 結以//著 講談社 91-ト
「あなたが青く見えるなら、リンゴもウサギの体も青くていいんだよ」
友達も多く成績優秀だが、本気になるものがなかった八虎が、ある一つの絵で藝大への入学を目指す。
YOASOBIの「群青」の元ともなった大人気作品。
※トライやるウィークの中学生がおすすめする本です!
『青い月の石』 トンケ ドラフト//著 岩波書店 94
月が青くなると特別なことが起きる。
ある日、地下世界の王が子どもたちの前に現れた。
ヨーストとヤンは、勇気を出して足跡を追うが・・
地上と地下をかけめぐる大冒険!
※トライやるウィークの中学生がおすすめする本です!
『アーベルチェの冒険』 アニー M.G.シュミット//著 岩波書店 94-シ
デパート開店の日、アーベルチェと三人の客を乗せたエレベーターが空へ飛び出してしまう。
人助けをしたり、革命に巻き込まれたり、アーベルチェは世界を旅することになります。
※トライやるウィークの中学生がおすすめする本です!
『からだにやさしい麹こんだて』 阿部 かなこ//著 大和書房 596
麹ってご存じですか?
私たちが日ごろ口にしている、醤油、味噌、酢、酒はすべて麹を使って発酵させたものなのです。
麹とは、蒸した米や麦、大豆に「種麹」をふりかけて「麹カビ」を繁殖させたものです。
この麹菌が繁殖するさいに生み出す酵素には、うれしい効果がたくさんあります!
保存がきく
生肉や魚を麹に漬けておくだけで保存期間が長くなります。
料理の味が決まる
麹が食材そのものの旨味を引き出してくれるので、たくさんの調味料を使わなくてもまろやかなやさしい味に仕上がります。
勝手においしくなる
麹菌の酵素で風味がよくなります。
酵素がでんぷんをブドウ糖に、タンパク質をアミノ酸に分解することで甘味や旨味が増します。
腸と肌にいい
食べるだけで悪玉菌が減り、腸内環境が良くなります。
そして、便通、生活習慣病予防などにも効果的とされます。
また、ビタミン代謝を促進して美肌作りに良いといわれています。
毎日の食卓を栄養たっぷりのごちそうにして心と体を元気に、健康に過ごされてはいかがでしょうか!
『これが最後の仕事になる』 米澤 穂信//著 講談社 F
最初の1行は、 「これが最後の仕事になる」で始まる24人の作家が描く短編集。
それぞれの最後の仕事とは?誰の何のためのどんな仕事?
気になりながら読むうちに、意外な展開に驚きつつ一気に読んでしまえる本です。
普段読まない作家との出会いも楽しめます。
『茶柱の立つところ』 小林 聡美//著 文藝春秋 914-コ
俳優 小林聡美さんの3年ぶりのエッセイ集
芸能人のエッセイ集なので
とにかくおしゃれでキラキラした世界のお話だろうと思っていたら
アレ、なんか違うぞ ?!
あっ、それ、わたしもある・・
わかりすぎる、その感じ・・
そんなお話がつぎからつぎへと
【私の、そして皆さんのありきたりな日々のどこかに、ときどき茶柱が立ちますように。】
※あとがきより
そんなあたたかい気持ちで書かれたエッセイです
『明けても暮れても食べて食べて』 はらぺこめがね//著 筑摩書房 596
イラストユニット・はらぺこめがねの絵本は子どもに大人気!
この本は、食べものまみれの日常を描いたイラストエッセイ集です。
どの絵を見ても、お・い・し・そ・う♪
『あなたを待ついくつもの部屋』 角田 光代//著 文藝春秋 F-カ
そこは、特別な時間を過ごすことができ、非日常を味わえる場所・・。
東京・大阪・上高地、3か所の帝国ホテルを舞台にした42編のショートショート。
ホテルを訪れる人、それぞれの物語をお楽しみください。
『積ん読の本』 石井 千湖//著 主婦と生活社 019
あれも読みたい、これも読みたい・・と思いながら、本を買う。
そして、読まずにだんだん増えていき、本は、どんどん積まれていく。
そんな積ん読の本について語られた、作家など12人の想いが詰まったインタビュー集です。
蓄積した本をどうすればよいかなど、整理収納アドバイザーが答える悩み相談のページもあります。
人には、それぞれ違った本の選び方や読み方など、本へのこだわりがあることに共感したり驚いたり、さまざまなジャンルの本が読みたくなる1冊です。
『カッコウの呼び声』 ロバート ガルブレイス//著 講談社 933-ガ
ハリーポッターの原作者J,Kローリングが、ロバート ガルブレイスのペンネームで発表したミステリー小説の第一作目です。
ロンドンを舞台に、元軍人の私立探偵コーモラン ストライクが活躍します。
彼のもとに、著名なモデルの女性が謎の死を遂げた事件の調査依頼が舞い込みます。
一見すると自殺と思われたその事件ですが、調べを進めるうちに深い闇と噓が明らかになっていきます。
助手のロビンとのやり取りも見どころのひとつです。
ガルブレイスならではの緻密なブロットと魅力的なキャラクター描写が魅力で、物語の世界へと引き込まれていきます。
サスペンス好きにはたまらない一冊です!
『大丈夫じゃないのに大丈夫なふりをした』 クルベウ//著 ダイヤモンド社 929-ク
今日は、しんどいな・・・ 疲れたな・・・
そんな落ち込むような時に、そっと寄りそってくれる本です
心に栄養を与えて、明日からの活力を持てるはず!
『生きる世界は、あなたが決めていい』 天宮 玲桜//著 ロングセラーズ 159
生きていると、時に、悩むこともあります
人間関係・子育て・健康・お金のことなど・・・
この本では、さまざまな事例をあげて、悩んでいる人が、幸せな道を見つけられるように、悩みごとの解決につながるヒントを紹介しています。
表紙をめくると、「あなたがあなたでいること。大切なのはそれだけです。」と著者。
まるで、本の中から語りかけられているかのように、優しい言葉が心に届く一冊です。
『メメンとモリ』 ヨシタケ シンスケ//著 KADOKAWA 726
メメンという名の姉と、モリという名の弟の3つの物語。
絵本のようですが、読み進めてみると何だか深い。
「メメント・モリ」とは、「死を想え、自分がいつか必ず死ぬことを忘れるな」という意味をもつ古代から伝わるラテン語だそうです。
”人は何のために生きてるの?生きる意味や目的って必要ですか?”
深いテーマだけど、日常のモヤモヤや悩みを包み込んでくれるような感じがしました。
人は、「思ってたのとちがう!」ってびっくりするために生きてるのよ。
思ってたのとちがうから、
世界はつらいし、きびしいし、たのしいし、うつくしい。
『山の上の家事学校』 近藤 史恵//著 中央公論新社 F-コ
男性対象の家事学校がる。
通う人たちの年代も事情も様々。
離婚後、荒れた生活を送っていた仲上は、「独身男性の寿命が極端に短い」との新聞記事が気になり、通うことにする。
学ぶうちに、料理を作ることや、身の回りを整えることの喜びや楽しさに気づく。
自分で生活をまわすことができるという気持ちは、確かな自信になる。
そしてなにより、パートナーや家族を助けるためでなく、その人自身が生きるために家事が必要であると教わる。
仲上が政治記者として仕事に追われているうちに、妻は不満を溜め込んで家を出て行った。
妻が求めていたのは、家をまわすことを他人事ではなく受け止めるということだったのでは・・・
少しでも早くそのことがわかっていれば、失わずに済んだものはたくだんあったかもしれない。
『「ハラスメント」の解剖図鑑』 宮本 剛志//著 誠文堂新光社 366
カスハラ(顧客ハラスメント)など不適切行為が頻繁に報道され、ハラスメントが社会問題となっています。
マルハラ? ジェンハラ? エイハラ? レイハラ? ソーハラ? ハラハラ?
法的に規制されるハラスメントの他に、想定外なハラスメントも!
その数に驚きますが、事例が複数あげられていて気づきがあるかも?
思わぬところで加害者、被害者にならないために・・・
※こちらも一読いかがでしょうか 『ハラスメント言いかえ事典』
『はじめての絵本』 磯崎 園子//著 ほるぷ出版 019
絵本は、赤ちゃんから大人まで年齢を問わず、読むことができる本です。
この本では、成長過程に沿った0~6歳までの年齢と大人に分けて、たくさんの絵本が紹介されています。
子どもの頃は、絵本の文章をそのまま受け取っていましたが、大人になってから絵本を読むと、その文章の他に意味が隠されているのではないかと深く考えることもでき、絵本を読む醍醐味を味わうことができます。
大人にオススメの絵本も紹介されており、久しぶりにワクワクして絵本を読みたくなる1冊です。
『家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった』 岸田 奈美//著 小学館 914-キ
山あり谷ありの人生と言うには、あまりに起伏の大きすぎる道のりを生きてきた著者・岸田奈美氏が、家族や自身の出来事を描く自伝的エッセイです。
中学生で父を亡くした後、ダウン症で知的障害の弟と、車いす生活の母を支えながら必死に生きた高校生時代。
一見悲観的に思われがちですが、もがきながら生きてきた彼女の言葉は、私たちが普段気づかず通り過ぎている思いに気づかせてくれます。
支えているようで、支えられていた。
助けいたつもりが、助けられていた。
それが岸田氏にとって「家族だから」じゃない、理由なのかもしれません。
兵庫県出身の著者の文中ユーモアには、泣き笑いしてしまいます。
『切なくそして幸せな、タピオカの夢』 吉本 ばなな//著 幻冬舎 914-ヨ
人生では、人と人が出会い、その中心には、いつもおいしい「食」があります。
温かいタッチのイラストもある著者の体験をもとに描かれたエッセイです。
読み終えると、心が穏やかになり、優しく包み込んでくれるお話です。
『手仕事をめぐる大人旅ノート』 堀川 波//著 大和書房 293
まずは装丁・・・
本の見た目がステキで思わず手に取りました
海外旅行なんて
この先行くことができるのかなぁと思いつつ・・・
人との関係は、仲良くなろうとか
好きになってもらおうと思うのではなく
目の前にいるその人の好きなところを
みつけるだけでいいんだなって気がついたんです (本文 はじめに)
この文におもわず、ふむふむ・・・
若い頃に感じたものが宝物とばかり思っていましたが
今回、小さな花を見て、50代になった今でも
「初めて」は集められるんだとうれしくなりました (本文 おわりに)
この文にちょっと、わくわく・・・
海外旅行にかぎらず(・・もちろん、行ってみたいけれど♬)
日々の暮らしの中で
いろいろなモノにコトに出会いたくなりました
丁寧に描かれたイラストもじっくりご覧になってみてください
『イグアナの花園』 上畠 菜緒//著 集英社 F-ウ
美苑は、人間には興味が持てず会話下手で人付き合いが苦手。
同級生から「空気が読めない」子として扱われていた。
だが、幼い頃から小さな生き物の声を聞く(感じる)ことができ、心を通わすことができた。
植物学者の父が急逝し、父の遺したアトリエでイグアナと暮らすことになる。
季節の移ろい、草木や花、風や光の描写が美しく、ありのままの美苑を受け入れようとする周囲の人たちが温かい。
そんな中で変化し成長していく美苑の心の動きがとても丁寧に描かれている。
『すみれ荘ファミリア』 凪良 ゆう//著 講談社 F-ナ
下宿すみれ荘の管理人を務める和久井一悟は、三人の下宿人たちとはお互いに気心の知れた仲で、穏やかな日々を過ごしていた。
そこに、小説家の青年が入居することになり、それぞれの関係性に変化が表れ始める。
今まで秘密にされていたことや思わぬ一面が露わになっていくも、関係は修復されるのか?
「世の中の人すべてが理解し合い、許し合えるなんでのは幻想だ。
だからといって希望を捨てることはない。
世界にも、心にも、グレーゾーンというものがあっていい。」
と、この一文に同感。
『バリ山行』 松永 K三蔵//著 講談社 F-マ
2024年第171回芥川賞受賞作品。
「バリ」=バリエーションルートの略。
本来の山登りとは違い、道なき道を自ら探しながら登るやり方の事です。
傾きつつある会社に不安を抱えながら仕事をする30代の会社員が主人公。
誰とも群れず、毎週一人でバリ山行をする同僚についてバリを体験しますが・・・
『バリはさ、ルートが合ってるかじゃないんだよ。
行けるかどうかだよ。
行けるところがルートなんだよ。』
『お菓子の旅』 甲斐 みのり//著 主婦の友社 291
開くページのあちこちに、懐かしくほっとする和菓子の数々が収められています。
村上春樹の小説にちなむコーヒーファクトリーや、島崎藤村が詩に詠んだ温泉宿なども紹介されていて、作家の思いに心が飛んでいきそうになったり・・・。
レトロで素敵なお菓子を味わいに、旅に出るのも良いかもしれません。
巻末にはお菓子の包み紙や手提げ袋、化粧箱なども紹介されていて、眺めているだけでも癒されます。
『まってました名探偵』 杉山 亮//著 偕成社 91-ス
探偵映画に感激して探偵になったミルキー杉山が数々の事件を解決する話。
今回は「はなれこじまさいふじけん」と「ミス・ラビットふたたびあらわる」の2つ。
どのお話のイラストにも事件解決のヒントがたくさん。
ミルキー杉山と事件を解決しよう!
※トライやるウィークの中学生がおすすめする本です
『黒魔女さんが通る』 石崎 洋司//著 講談社 91-イ
”キューピットさん”を呼び出そうとして、間違って黒魔女の”ギュービッドさん”を呼び出してしまったチョコ(黒鳥千代子)。
ギュービッドの指導のもと、黒魔女修行がはじまります。
キャラがとても個性的で読んでいてとてもおもしろいです!
私はPart 16の『黒魔女さんのホワイトデー』が一番好きです!
6年1組編や、外伝もすごくおもしろいので、あわせて読んでみてください。
※トライやるウィークの中学生がおすすめする本です
『十角館の殺人』 綾辻 行人//著 講談社 F-ア
「十角館」という奇妙な館を訪れた大学のミステリィ研究会の7人。
彼らを襲う連続殺人。
はたしてその犯人は・・・!?
1987年刊行以来読者をだまし続けている「衝撃の一行」をぜひ味わってみてください!
あの一行の衝撃は、今でも忘れられません。
記憶を消してもう一度読みたい本格ミステリの名作です。
※トライやるウィークの中学生がおすすめする本です
『うちのネコ、ボクの目玉をたべちゃうの?』 ケイトリン ドーティ//著 化学同人 491
ネコちゃんの本ではありません。
死との向き合い方についての本です。
子どもから送られた「死」についての疑問に、アメリカの葬儀ディレクターである筆者が、面白く、誠実に答えています。
突拍子もない質問もありますが、つい「それ知りたい!」と思ったり、クスッと笑えてしまったり・・・。
人が必ず迎える「死」について笑顔で読める本です。
『九番目の雲』 山岡 ヒロアキ//著 講談社 F-ヤ
37歳の営業マン吾郎が、仕事や家族の問題を諦め逃げ続けていた自分と向き合い、成長していく物語です。
人生の苦境に立たされながらも、自分自身や周囲の関係を見つめ直し、新たな一歩を踏み出していく姿が描かれています。
※インターンシップの高校生がおすすめする本です!
『テヘランのすてきな女』 金井 真紀//文と絵 晶文社 367
イランでは、満9歳以上の女性は、公共の場所ではヘジャブとよばれる頭髪を隠すためのスカーフと身体の線を隠すためのコートの着用が、法律上義務付けられている。
ところが、2020年秋「反スカーフデモ」が、全土に拡大。
イランの女性たちの生の声を聞くべく著者は、イランへ向かう。
さまざまな立場やさまざまな職業の女性を取材したインタビュー&スケッチ集。
著者が、前世界の全員に言いたいこと。
それは、「横暴な権力者、古くさい思想、クソ差別、自信を失いそうになるたくさんの落とし穴に負けずに、それぞれがその人らしくいられますように。
この人生を味わって進んでいけますように。」と。
※同じ作者の『パリのすてきなおじさん』も合わせておススメします。
『旅の彼方』 若菜 晃子//著 東京KTC中央出版 290.9
旅に出る理由や目的は人それぞれ。
著者の場合は、見知らぬ国のできれば地方、初めて訪れる街や山や自然を歩き、そこに生きる人々に出会い、たとえわずかな間でもその片隅で暮すように旅するという。
街角の風景はもちろん、道ばたに咲く小さな花、風が運ぶ香り、出会った人の笑顔、交わした言葉など、何でもないようなことが、のちの自分に繋がっていく大切なものになると気づかせてくれる一冊です。
※同じ作者の『旅の断片』も合わせておススメします。
『最後に”ありがとう”と言えたなら』 大森 あきこ//著 新潮社 673
納棺師というお仕事を通して、様々な方の”死”への向き合い方を経験された著者の思いが詰まった本でした。
私も数年前に父の死を体験しましたが、「こうしてあげればよかった・・・」「ああしてあげればよかった・・・」と後悔ばかりが残ります。
自分自身や家族に対する”死”に対する覚悟を持ちたいと思いました。
『ボス猫メトとメイショウドトウ』 佐々木 祥惠//著 辰巳出版 645
引退した競走馬がどのような生活をおくっているか、全く知らなかったので、この本をきっかけに知ることができ、猫との生活風景に癒される反面、厳しい現実を知ることができました。
どんな一生を送るにしても、動物も人間も共にのびのびと過ごせる平和な世界であって欲しいと願うばかりです。
『逃げたっていいじゃない』 香山 リカ//著 エクスナレッジ 159
こころがつらいときは、逃げていい。
この本では、苦しい職場・家族・SNSなどから、どうやったら逃げることができるか、さまざまなアイデアが紹介されています。
決して、逃げることは悪いことじゃない。
つらいことや苦しいことから自分を守る方法として、「逃げる」という選択肢があるということを教えてくれます。
『脳の筋トレ!思い出しおりがみ』 古賀 良彦//監修 主婦の友社 754
子ども時代はすらすら折れたおりがみも、大人になると折り方も忘れがちです。
この本では、写真と図によって折り方が詳しく説明されており、鶴やかぶとなどの懐かしいものから、つるし飾り・四季のカレンダーなど、普段使いできるものが紹介されています。
久しぶりに折ると、できた時の達成感が味わえ、楽しい時間を過ごせます。
『めざせ!ムショラン三ツ星』 黒柳 桂子//著 朝日新聞出版 326
~刑務所栄養士、今日も受刑者とクサくないメシ作ります~
☆☆☆ミシュランならぬムショラン三ツ星をめざして☆☆☆
入口から幾重もの扉を開けてたどり着く「炊事工場」略して「炊場」。
管理栄養士である著者が、調理経験のほとんどない男子受刑者とチームになって刑務所の給食作りに奮闘する。
刑務所の中の日常にも笑いあり、涙あり。
そうなのか・・・と驚いたり、なるほどな~とうなずいたり、クスッとなるエピソードも多く、面白おかしく読むことができました。
第1章 みりんもバナナの皮もアルミ包装もNG!
第2章 「みょうがはどこまでむくんですか?」
第3章 全国刑務所人気ナンバーワン!「どんぶりぜんざい」
第4章 「愛情の安売りはよくないですよ」とたしなめられて
『不登校になって本当に大切にするべき親子の習慣』 菜花 俊//著 青春出版社 371
もし子どもが学校を休みがちになったら・・・。
「いつになったら学校に行くの?」「なにか理由があるの?」
原因を探したり、自分を責めたりと多くの親御さんは苦しむでしょう。
「学校に行きたくない」と言われて、「行きたくないなら行かなくていい」と認めてあげられる大人はどのくらいいるでしょうか?
☆不登校であっても、つらい、悲しいと悩まない
☆親自身が「自分のために」したいことをする ”自分ファースト”
その姿を見て、子どもはきっと気持ちを変化させていく。
子どもはこんな考え方、受け取り方をするんだということを感じることができます。
『加藤英明、カミツキガメを追う!』 加藤 英明//著 学研プラス 48
世界中の爬虫類を追う爬虫類ハンター、加藤英明先生。
人をかむこともある危険なカミツキガメを捕まえる方法とは?
そもそもなぜ、アメリカのカメが日本の水辺にいるのか。
自然と人との関係を見つめ直す、熱いドラマが始まる。
※トライやる・ウィークの中学生がおすすめする本です!
『めくって学べるきかいのしくみ図鑑』 学研プラス 53
みなさんが普段使っているエレベーターがどのようにして動いているか分かりますか?
エレベーターの絵をめくると、人が入ってから降りるところまでのしくみを見ることができます。
身の回りにあるきかいのしくみを知ってみませんか!
※トライやる・ウィークの中学生がおすすめする本です!
『心の森』小手鞠 るい//著 金の星社 91-コ
父の仕事でアメリカの小学校に引っ越すことになった少年の名は響。
ある日、家の裏庭の森で響は少女に出逢う。
少女は何も話さず笑顔で見つめるだけ。
名前をたずねると、一輪の花を手に渡す。
その少女の名前はデイジー。
響はデイジーに会うようになった。
でも、デイジーには思いもよらない秘密があった。
※トライやる・ウィークの中学生がおすすめする本です!
『四つ子ぐらし』ひの ひまり//著 KADOKAWA 91-ヒ
それぞれ違う環境で育った中学生の四つ子「一花、ニ鳥、三風、四月」。
そんな四つ子が「未成年自立生活練習計画」で一緒に暮らすことに!?
色んなトラブルが子どもたちに巻き起こるが、姉妹のみんなと力を合わせて乗り越えていき・・・?
恋と友情、そして家族の大切さが分かるストーリー!
シリーズものなので他の巻もぜひ!
※トライやる・ウィークの中学生がおすすめする本です!
『グリムのむかしばなし』グリム//著 ワンダ・ガアグ//編 のら書店 94
「ヘンゼルとグレーテル」「かえるの王子」「シンデレラ」など様々なグリム童話を全7話収録。
有名なあの童話にユーモアあふれる絵が添えられた物語。
お話の世界に引き込まれるほど、ワクワク・生き生きとした本になっています。
※トライやる・ウィークの中学生がおすすめする本です!
『すべて話し方次第』一田 憲子//著 KADOKAWA 361
人と会って、人と話す生活がようやく少しずつもどってきました
誰かと話すということは
自分一人で生きているんじゃないと知ること。
本当にそうなんだとこの数年間で実感しました
「話す」ことを大事にしてみたら、
今のままの私でありながら 新しい扉が開く。
そうだとしたら、とっても気になりませんか?
これからの暮らしの中での【話し方】が♪♪♪
『うらはぐさ風土記』中島 京子//著 集英社 F-ナ
30年ぶりにアメリカから帰国し、武蔵野の一角「うらはぐさ」地区の伯父の家に一人で住むことになった沙希。
そこは、彼女が学生時代を過ごした場所でもあり、今も、古い街並みや昔ながらの商店街が残っている。
読み進むうちに、その風景に懐かしさを覚え、個性豊かな近隣住民たちにも親しみがわいてくる。
地域の再開発の問題が浮上するが、それに向き合う住民たちの姿勢もいい感じ。
時の流れとはいえ、変わるものもあれば、変わらないものもあると気付かされる。
街も人も、これから先の変化をどう受け止めるのか、「うらはぐさ」の未来が気になってしまう。
『注文に時間がかかるカフェ』大平 一枝//著 ポプラ社 496
吃音の人に出会ったことがない。
その理由は本を開いてすぐにわかった。
吃音を持つ人のほとんどは、人前に立つ仕事を選ばないからだ。
メニュー名も「いらっしゃいませ」も言えない。
電話対応なんてもってのほか。
吃音を理由に接客業をあきらめていた高校生や大学生が、夢をかなえるため「注文に時間がかかるカフェ」を立ち上げた。
吃音を持つ若者には接客という経験を通して自信を、来場者には交流を通して吃音についての理解を、というコンセプトである。
カフェでの体験から若者たちが変化していく様子は素晴らしいが、今までどれだけのことを諦めてきたのだろう、と思うと胸が締め付けられる。
吃音を知るための第一歩としておすすめの一冊。
『ある行旅死亡人の物語』武田 惇志、伊藤 亜衣//著 毎日新聞出版 916
ご存知でしょうか?「行旅死亡人」。
初めて聞くという方も多いのでは?
それは、名前や住所など身元が判明せず、引き取り人不明の死者を表す法律用語なのです。
2020年4月、兵庫県尼崎市のとあるアパートで女性が孤独死した。
身元が分かるものが何もなく、残っていたのは星型マークのペンダント、数十枚の写真、「沖宗」と彫られた印鑑、そして・・・現金3400万円!!
わずかな手がかりをもとに記者2人が女性の謎を追い、その「行旅死亡人」が本当の名前と半生を取り戻すまでを描いたノンフィクションです。
記者魂のすごさと、人の人生の儚さと尊さを実感させられます。
『エレガントな 毒 の吐き方』中野 信子//著 日経BP 361
脳科学と京都人に学ぶ「言いにくいことを賢く伝える」技術とは。
もくじには・・・
①NOを言わずにNOを伝えるコミュニケーションが今こそ必要な理由
②「シチュエーション別」エレガントな毒の吐き方を京都人に聞きました
③「困った」「イヤだ」を賢く伝える7+3のレッスン
など、よくありそうな場面設定での例が挙げられていて、おもしろくわかりやすい内容です。
著者曰く・・・
ストレスを感じながら、密な関係を互いに無理をして維持するよりも、適度な距離感で気楽に気持ちよくお付き合いができることが大切。
うまくコミュニケーションをとって、お互いにいい時間を過ごしたい。
人間にとって、人生には有限の時間しか与えられていないから・・・と。
『幽霊人命救助隊』高野 和明//著 文藝春秋 F-サ
自殺した浪人生高岡裕一は、神に「仲間と共に自殺志願者100人の命を救うことを天国行きの条件とする」と命令される。
人々を救助する中で感じる気持ち「人生とは」ということについて改めて考えさせられる。
救助する最後の1人まで目が離せない!
※初任者研修で来れれた市内中学校の先生がおすすめする本です!
『解きたくなる数学』佐藤 雅彦、大島 遼、廣瀬 隼也//著 岩波書店 410
「数学」と聞くと読む気がなくなる方は是非!!
読むというより見て考えるというものです。
日常にある「窓」や「チョコレート」を数学的な視点で見ることができます。
日常にある「当たり前」を疑ってみてはいかがでしょうか。
世界はさらに大きく広がっていきます。
※初任者研修で来れれた市内中学校の先生がおすすめする本です!
『君色パレット』高田 由紀子、光用 千春他//著 岩崎書店 91
「君色パレット」は、多様性をテーマに、主人公と様々な距離間の人たちとの物語を収録したシリーズです。
この世界に生きるあらゆる人たち、そして自分自身のことを、大切に見つめるきっかけとなりますように・・・!
※初任者研修で来れれた市内中学校の先生がおすすめする本です!
『おもろい以外いらんねん』大前 粟生//著 河出書房新社 F-オ
お笑いコンビ〈馬場リッチバルコニー〉が解散するまでの話。
幼馴染の咲太と滝場、転校生のユウキという仲良し3人組が、笑いと傷をめぐって葛藤する10年間の物語である。
本当の「おもしろさ」とは何か、考えるきっかけになる一冊。
※初任者研修で来れれた市内中学校の先生がおすすめする本です!
『ある男』平野 啓一郎//著 文藝春秋 F-ヒ
シングルマザーの里枝は息子の悠人と実家に戻り、家業の文房具店を切り盛りしていた。
ある日客の大祐と恋に落ち、再婚、悠人の妹・花も誕生した。
穏やかな家族の時間を過ごしていたが、仕事中の事故で大祐は亡くなってしまう。
疎遠にしていた大祐の兄と連絡を取ったことから、大祐は「谷口大祐」ではなく、誰かが戸籍ごと「谷口大祐」なりすましていたことが判明する。
里枝は自分の夫だった男の調査を弁護士の城戸に依頼する。
一見エリートの城戸にも、人に触れられたくない内面があった。
城戸は男の過去を調べるうち、その人生に自分を重ねていく。
『そこに工場があるかぎり』小川 洋子//著 集英社 914-オ
小説家でエッセイストの小川洋子さんが、子どもの頃から抱き続けている工場への思い入れを、作家になった今の自分の言葉で表したのが本書だとか。
小川さんの好奇心、探求心、工場愛は特別なモノ!
グリコの工場では・・・
「ビスコのビスケット部分の生地は、その日の天候や湿度、ガスの具合によって、ビスコマイスターという職人が配合を調整している」とのこと。
工場で作られるとはいえ、人と機械が融合して一生懸命作っている。
私たちにもなじみのあるお菓子は、人間の手の温もりが伝わる製品だったのです。
知ってしまったあとは驚くほどに認識が変わります!
「━製造されている現場など思い浮かべもしないで当たり前に使っている何かが、この世のどこかにある工場で、人知れず製造されている。
今も世界のどこかで、誰かが何かを作っている。
この想像が、どれほど私の救いになっているか知れません。
いくら感謝してもしきれない気持ちです。━」 本書のあとがきより
『意味変語彙力帳』神永 曉//監修 総合法令出版 814
! 言葉の意味は時代とともに変わる!
「本来の意味(本意味)」も「変化した意味(意味変)」も知って、コミュニケーションを円滑に。
マンガでも解説されていて読みやすい!
どっちの意味で使ってる? 「煮詰まる」 →行き詰る
→結論が出る
「触りの部分」 →話の冒頭
→話の中心、聞かせどころ
どちらも間違いじゃない!!
『モノのお手入れ・お直し・作りかえ』暮らしの図鑑編集部//編 翔泳社 590
大切なモノを長く使うために、 たくさんのアイデアが詰まった一冊です。
日々の生活のヒントにも。
『逃げても、逃げてもシェイクスピア』草生 亜紀子//著 新潮社 289-マ
翻訳家の松岡和子さんが、28年間でシェイクスピア劇37作品を新訳しました。
400年前の英語で書かれたシェイクスピア劇を、今を生きる私たちの日本語にしていくとは、どのような作業なのか・・・。
全世界で上演されてきた戯曲には、たくさんの先行訳があるが、なぜ彼女が訳すことになったのか、そのいきさつとこだわりがこの一冊にこめられています。
読後は、自分から遠いところにいたシェイクスピアを少し身近に感じました。
※『シェイクスピア全集』全33巻 松岡和子訳 筑摩書房 932
文庫のコーナーにあります。表紙は安野光雅さんの絵です。
『私たちの特別な一日』飛鳥井 千砂、寺地 はるな他//著 東京創元社 F
人生の節目に催される冠婚葬祭の行事。
時代の移り変わりとともに、そのありようは変化しつつあります。
現在の、そしてこれからの私たちと冠婚葬祭をテーマに書かれた短篇集です。
○『もうすぐ十八歳』 飛鳥井 千砂//著
○『ありふれた特別』 寺地 はるな//著
○『二人という旅』 雪舟 えま//著
〇『漂泊の道』 嶋津 輝//著
○『祀りの生きもの』 高山 羽根子//著
○『六年目の弔い』 町田 その子//著
『本日のメニューは。』行成 薫//著 集英社 F-ユ
おいしいごはんと5つの物語。
どのお話も、あたたかい人間関係が描かれていて楽しく読めます♪
料理の描写もおいしそうで、食欲をそそられます。
○「四分間出前作戦」・・・入院中の父親に中華そばを出前したい兄弟と、それを助ける大人たちのお話し。
○「おむすび狂詩曲」・・・母親のマズメシに悩まされている女子高生と、おむすび屋店主のお話。
○「闘え!マンプク食堂」・・・大盛りが売りの大衆食堂と大食い青年の対決のお話。
○「或る洋食屋の一日」・・・50年続いた洋食屋の閉店を迎えた一日を描いたお話。
○「ロコ・モーション」・・・脱サラし、キッチンカーを営業することになった若い夫婦のお話。
『犬と一緒に生き残る防災BOOK』犬防災編集部//編 日東書院本社 645
「犬の防災」でまず大事なことは、物を揃えることではなく、あらゆるケースを想像することだそうです。
この本では、普段から備えるべき物や知識、いろんなケースの災害発生状況と避難生活について、イラストと共にアドバイスやコツを紹介しています。
その他、ペットシーツの活用術や車中泊グッズ、犬がケガをした場合の応急処置の方法なども載っています。
災害がおきたとき、家族の一員である愛犬と一緒に生き残るため、まず大事な「想像力」が身につき、備えに役立つ一冊です。
『パトリックと本を読む』ミシェル・クオ//著 白水社 936-ク
貧困や周りの劣悪な環境から犯罪を犯してしまった少年を【本を読む】ことで救った実話にもとづく物語です。
知識を得ることで救われる人生があるのだと思い、読書の大切さを感じました。
『手はポケットのなか コーダとして生きること』ヴェロニク・プーラン//著 白水社 959-プ
この本は、2022年アカデミー賞作品賞を受賞した「コーダあいのうた」の原案になったものです。
私は先に映画を見たのですが、日常生活の描写や葛藤が若干異なっていて、それぞれのお国柄が出ていて面白いなあと思いました。
家族愛にあふれた作品だと思いますので是非ご一読ください。
『私のカレーを食べてください』幸村 しゅう//著 小学館 F-ユ
成美は、小学生の頃、担任の先生が作ってくれたカレーライスが忘れられない。
調理師学校に進学し、その味を再現しようとカレー研究に没頭する。
香りに誘われて入ったお店で口にしたカレーに衝撃を受け、”カレーの味を盗むまで、あの店に通い続けよう!”と決心する。
店長と出会って創意工夫を重ね、お客様のためにカレーを作る。挫折を経験して立ち上がるまで・・・
※「カレー祭り」のカレーがどれもおいしそう。きっとカレーが食べたくなります。
スパイスの本も併せていかがでしょうか『いちばんくわしいスパイス便利帳』世界文化社 588
『世界でいちばん変な虫 珍虫奇虫図鑑』海野 和男//写真と文 草思社 486
この本は世界の奇妙な形や模様の虫が載っている本です。
自分が最も好きなページはp36とp37で、奇妙な形をしたツノゼミが多く載っています。
他にも奇妙な虫が多いので、ぜひ読んでください。
※トライやるウィークの中学生がおすすめする本です!
『円卓』西 加奈子//著 文藝春秋 F-ニ
八歳にして「孤独」に憧れるこっこは口が悪く、意味不明な行動でみんなを驚かせる。
そんなこっこは突然ぽっさんから謝られ、初めて死ぬことを「寂しい」と感じる。
同時に、これまでなかった感情があふれ出す。
失われた感覚を呼び覚ます一つの物語。
※トライやるウィークの中学生がおすすめする本です!
『20代で得た知見』F//著 KADOKAWA 914-エ
自分の心を動かしたものだけが、真のインプットである。
誰かの心を動かしたものだけが、真のアウトプットである。(p106)
たった三秒で終わった出来事でも、それがもし永遠に記憶に残るほどのものなら、それは永遠より長い。(p174)
追い詰められたら、ニャーン、とでも言っておきなさい。(p66)
著者が20代の時に教えられたこと、気づいたこと、感じたことが詰まった1冊です。
待ち合わせの相手を待つあいだに。家事と家事のすきまに。眠る前に少しだけ。
どこから読んでもいいのです。
ぱっと開いたページで、クスっと笑えるような、ほほうと感心するような、私が考えたことにしていつか誰かに語ってやろうと思うような、言葉と出会えます。
『お茶でかんたん飲む薬膳 食材1つ足すだけ』植木 もも子//著 家の光協会 498
その昔、お茶は薬として飲まれていたといいます。
薬膳と言っても難しいことではないのです。
いつもの緑茶にレモン、麦茶におろししょうが、紅茶にマーマレード、コーヒーにココアなど、食材を1つ足すだけで、お茶の効能を高めることができると書かれています。
おいしいお茶ができるのを想像しながら淹れることで、気持ちが落ち着きリラックス。
忙しい日々のなかで、そんな時を過ごすことも、薬膳の養生となるそうです。
効能とお茶のレシピも載っています。
本書の中で使われている茶器もステキです。
『鎌倉駅徒歩8分、空室あり』越智 月子//著 幻冬舎 F-オ
鎌倉駅から徒歩8分、木々と季節の花に囲まれた古い洋館のシェアハウスが舞台。
入居者たちはちょっとワケあり。
様々な悩みや複雑な過去を抱えている彼女たちが、ここで見つけた新しい形の絆とは...。
読み進むうちに、コーヒーの香りに包まれた小鳥のさえずりが聴こえてくるような心和らぐ一冊です。
『つぎはぐ、さんかく』菰野 江名//著 ポプラ社 F-コ
惣菜と珈琲のお店「△(さんかく)」
そこで暮らしているきょうだい 兄・妹・弟
晴太・ヒロ・蒼
お互いに
大切にしあいながら
幸せを願いあいながら
暮らしている
たとえば
取り決めたわけでもなく
誰かが言い出したわけでもないけれど
”3人のうち、誰かの話を残りの2人で話すのは、ルール違反″
でも
このきょうだいには、それぞれ事情があって
今、こうして3人で暮している
毎日を懸命に生きている3人から
あたたかい気持ち、あきらめたくない願い、強く生きていく思いを
受け止めてみませんか・・・
〈選考員満場一致!第11回ポプラ社小説新人賞受賞作〉
『NHKが悩む日本語』NHK放送文化研究所//著 幻冬舎 810
日本語って難しいと思ったことはありませんか?
・100歳をこえて生きる、というときの漢字は「超える」?「越える」?
・赤ちゃんパンダは「1匹」?「1頭」?
・2024年の「幕開け」「幕開き」どちら?
・「数日」は何日くらい?
などなど普段何気なく使っている言葉ですが、そういわれると・・・
「へー!、なるほど、そうなんだよね~」そんなふうに思える内容が多い本です。
『愛するよりも愛されたい』佐々木良//訳 万葉社 911.1
万葉集が令和言葉・奈良弁で訳されています。
古の人に想いを馳せ、身近に感じられる一冊です。
『100万回死んだねこ』福井県立図書館//編 講談社 015
気になってた本の覚え間違い、あるあると笑いながらお読みいただけます。
図書館員のお仕事の一つは、本と人をつなぐこと。
お読みになりたい本を精一杯探します。
間違っていても、うろ覚えでも、どうぞお気軽にお尋ねください。
『自分を休ませる練習』矢作 直樹//著 文響社 159
最近、ゆっくり休めていますか?
ついがんばりすぎてしまうことが、くせになっていませんか?
この本では、がんばりすぎる人は「いいかげん」になる、長くゆっくり呼吸する、ぼーっとする練習など、ほどほどに生きるコツをいくつか紹介しています。
忙しくて休めない・・・そういう時にも、読むだけで休んだ気になれ、不思議と心が軽くなる1冊です。
『シェフ』 ゴーティエ・バティステッラ//著 田中 裕子//訳 東京創元社 953-パ
美味しい食事を食べることは、人生の楽しみの一つだと思います。
この本に出てくるようなミシュランガイドの星を獲得するシェフのいるレストランには縁遠く、料理の名前を見ても味の想像すらできないですが、
このような料理を生み出すシェフの苦労や喜び、孤独や賞賛など様々な感情や行動を知ることができました。
是非手に取って、「料理の世界」を味わってください。
『空の辞典』 小河 俊哉//著 雷鳥社 451
当たり前にある空だけど、毎日違う表情を見せてくれる。
見上げた空の美しさに感動したり、あの時、あの場所で見た空は、もう見られない貴重な空の顔。
あなたが見上げたその空に名前があることは知っていますか?
この本にはあなたが見た空の名前がきっとみつかるはず。
あの時の空の名前を探しながら、美しい空の表情に癒されてみるのはいかがでしょうか?
『本を読んだら散歩に行こう』 村井 理子//著 集英社 914-ム
亡くなった兄、両親との関係、義理の両親の介護、双子の息子の受験、自分の病と仕事など、
相当大変な日々を過ごされているはずなのに、ちっともそれを感じさせないのはどうして?
それは「常に寄り添い、人生を伴走してくれる本があったから。」と著者。
「本は私が必要とするそのときまで、じっと動かず、静かにそこで待っていてくれる。
人間は信用できない。信用できるのは、本、それから犬だけだ。」(本文より)
著者のこの苦しい数年を救ってくれた本の中から、考えさせられる一冊、楽しい一冊、
気軽な一冊、見て楽しい一冊が紹介されています。
これは、エッセイ+読書案内を兼ねたおトクな本です。
『おひとりさま日和』 大崎梢 岸本葉子 坂井希久子 咲沢くれは 新津きよみ 松村比呂美//著 双葉社 F
テーマは、「ひとりの生活」。
6人の女性作家の書き下ろしエッセイ集です。
自分に合った気楽で自由を満喫できる生活って?
6話ともそれぞれ違うけれど、共感できるところも多く楽しめました。
『とあるひととき』 花王プラザ//編 平凡社 914
テーマは、一日の三つの時間帯。
「朝」のひととき、「夕暮れ」のひととき、「午後11時」のひととき。
14人の作家のエッセイ集です。
日々の暮らしの中で、自分を取り戻しホッとできる時間は、特別なもので大切にしたい。
自分にとってそんなひとときって何時なのかなあ・・・。
日々を振り返るきっかけになる一冊です。
『万葉の愛をたずねて』 稲田 宰//著 文芸社 911.1
万葉集の中で、愛がテーマの和歌だけを厳選した解説集です。
古典の言葉は難しくて分からない・・・
でも、いつかは読んでみたい!と思っていた万葉集。
短い言葉で解説されているので楽しく読め、万葉集が身近に感じられる一冊です。
『世界のかわいい村と街』 パイインターナショナル//編著 パイインターナショナル 290
童話に出てくるような世界にあるカラフルでかわいい街並みと建物を紹介した写真集です。
昔ながらのノスタルジックな街や花いっぱいのロマンチックな街・・・
本を開くと、色鮮やかな街並みに目を奪われ、まるで童話の世界に入り込んだように、ワクワクしながら読める一冊です。
『犯罪心理学者が教える 子どもを呪う言葉・救う言葉』 出口 保行//著 SBクリエイティブ 379
少年鑑別所に勤務し、1万人の犯罪者・非行少年の心理分析を経験した著者が犯罪の具体例を交え、心理学的な子育てのアドバイスを伝える。
”「うちの子に限って大丈夫!」という家庭でこそ読んでほしい”
「早くしなさい」「何度言ったらわかるの」「勉強しなさい」等、親がつい言ってしまいがちな言葉を子どもはどう感じ取っているか、
押し付けになっていないか考えてみたことはありますか。
「よかれと思って」発した事が知らず知らずのうちに子どもを苦しめているかも?
子どもにとって、親が自分に真剣に向き合ってくれていると感じることが大事なのだそうです。
『11番目の取引』 アリッサ・ホリングスワース//作 もりうち すみこ//訳 鈴木出版 93-ホ
アフガニスタンから逃れ、祖父とともに難民となった少年サミ。
祖父の生きる術であり、心の拠り所だった伝統楽器ルバーブが奪われた!
サミは友達の助けを借りて物々交換を始め、ルバーブを買い戻す決心をする。
紛争の過酷さの中にあるもてなしの心や名誉、友情や希望・・・心が洗われるような気持ちなりました。
大人の方にもぜひ読んでもらいたい一冊です。
『28文字の捨て方』 yur.3//著 主婦の友社 597
● 物に愛着を持てない人ほど使わないものに執着する。
●「何かに使える」と思うものほど ほとんど何にも使わない。
気持ちがなぜか晴れないとき
わたしは無性に「片づけ」がしたくなります。
でも、やり始めるとかえって、しんどくなることが・・・
その原因は、「これ、どうしようか」と捨てる捨てないを考える作業
この本は
背中を押してくれます、だなんてそんなやさしいものではありません。
ぐいぐいぐいっと、手をひっぱってくれます(※くれました)
爽快な気持ちですすめる「片づけ」に
読んで頭をスッキリ
片づいて目の前がスッキリ
そして、最期は心もスッキリ
トリプルスッキリ いかがでしょうか
『五十八歳、山の家で猫と暮らす』 平野 恵理子//著 亜紀書房 914-ヒ
私もこの年齢となり 境遇は違えどいろいろ悩むことも多く 不自由なりの のんびりした生活を楽しめたらと思うようになりました。
この本を読んで、これからの人生のことちょっと考えてみるのもいいかもしれませんね。
イラストもとても素敵です。
『星がひとつほしいとの祈り』 原田 マハ//著 実業之日本社 F-ハ
7つのお話から成る短篇集。
旅好きの著者らしく日本各地が舞台に。土地の方言も味わいがあり温かい。
平凡(?)に暮らす人々にも物語がある。
年代も抱える事情も違いはあるが、それぞれが精一杯生きていて、その行く末には、星の瞬きのような明るさが感じられる。
静かな余韻の残る一冊です。
『ヨルガオ殺人事件 上・下』 アンソニー・ホロヴィッツ//著 山田 蘭//訳 東京創元社 933-ホ
前作『カササギ殺人事件』の続編となる今作は "一粒で二度おいしい” 体験が得られます。
犯人を当てるためにもう一つ作品を読める!
ミステリーファンなら嬉しいと思います。
是非本格ミステリーを十二分にお楽しみください。
『大人の生き方 大人の死に方』 海原 純子//著 毎日新聞出版 498
著者は、医学博士・心療内科医・大学教授の海原純子さん。
昨今の閉塞感の原因は、ステキな大人が少ないこと。
魅力ある大人が増えると、若者たちもあとに続くのではないかと、海原さんは考える。
そこで今一度、年を重ね、自分独自の人生を歩むことについて考えるひとときを作ってほしい。
生の延長線上にあるのが死。
死を意識することは充実して生きることにつながると、新聞連載原稿に加筆したのが本書。
身辺の日々の出来事を感じたままに書かれているので親しみやすく、視野を広げ新しい視点を得ることの大切さが伝わる。
『さよたんていのおなやみ相談室』 さよたんてい//著 ぴあ株式会社関西支社 159
さよたんていは11歳の女の子。あらゆる人のどんなお悩みも解決してくれます。
一つ一つのお悩みに真剣に向き合う彼女の言葉は、シンプルで的確。
例えば P120 「運命の人はいつ現れるのでしょうか」
いつ現れるのかはわかりません。だから運命なんじゃないですか?
P246 「楽しい人生にしたいです。どうすればいいですか?」
あなたしだいです。ゆめをもちましょう。
どのページからでも開いてみてください。日々を過ごすためのヒントがもらえるかもしれません。
『小日向でお茶を』 中島 京子//著 主婦の友社 914-ナ
2018年10月~2022年9月まで、雑誌「ゆうゆう」に連載したエッセイが本になりました。
50代になった著者の体のこと、美味しい食べ物、料理や旅行の話、コロナ禍の生活の様子が綴れています。
あとがきには、「人生は長い。できるだけ正気を保って、退屈せずに天寿を全うしようと思うなら、それなりに楽しめるなにかをみつけないと。」とあります。
そして、なにかをするかしないかは、年齢ではなくて、人なのだと。
自分にも共感できるところがたくさんあり、元気をもらえる一冊でした。
『世界の美しい動物園と水族館』 パイインターナショナル//編著 パイインターナショナル 480
世界各地にある73の動物園と水族館が、鮮やかで美しい写真とともに紹介されています。
宮殿の敷地内にある動物園、そして動物園にいるはずのあの大きな動物がなんと!水槽の中に・・・
想像を超える魅力があふれ、ワクワクしながら読める1冊です。
『「あの人」のこと』 久世 光彦//著 河出書房新社 770
「あの人」って?
小説家でもあり、数多くのテレビドラマの演出やプロデュースを手がけてこられた久世光彦さんが関わったあの人たちのことを
エピソードとともに記されています。
その中にはあちらへ旅立たれた人もあり、当の久世さんも既にあちらの人。
読むうちに、まるで自分もあの人たちとともに時を過ごしたかのような懐かしい気持ちになってしまいました。
『88歳、しあわせデジタル生活』 若宮 正子//著 中央公論新社 007
”デジタル”や”インターネット”などの用語を、例え話を用いて分かりやすく解説し、パソコンやスマートフォンを
活用した著者の日々の暮らしの様子、デジタル機器を使うときの17のヒントやコツを紹介しています。
”デジタル”という言葉を聞くだけで、難しそう・・・と苦手意識がある方も、そそっかしい著者の経験や出てくるヒントに、
なるほど!とワクワクしながら楽しく読める1冊です。
『ルルとララのおしゃれクッキー』 あんびる やすこ//作・絵 岩崎書店 91-ア
はじめての子にもわかりやすい!
さてさて、まんなかの木にクッキーの実はなるのかな?
※トライやる・ウィークの中学生がおすすめする本です!
『世界でいちばん変な虫 ~珍虫奇虫図鑑~』 海野 和男//写真と文 草思社 486
この本は世界の奇妙な形や模様の虫がのっている本です。
自分が最も好きなページは、P36と37で、奇妙な形をしたツノゼミが多くのっています。
他にも奇妙な虫が多いので、ぜひ読んでください。
※トライやる・ウィークの中学生がおすすめする本です!
『西表島フィールド図鑑』 横塚 眞己人//写真・著 実業之日本社 462
この本は西表島の自然について書かれたものです。
特に昆虫類のページがオススメで、本の中でも最もページ数が多いです。
また、付録として地図もあり、旅行する時役立つと思います。
※トライやる・ウィークの中学生がおすすめする本です!
『ギフテッドの光と影 ~知能が高すぎて生きづらい人たち~』 阿部 朋美・伊藤 和行//著 朝日新聞出版 371
「ギフテッド」=「天才」?
「ギフテッド」とは、どのような人たちで、どのような特性を持っているのか?
その実情は、あまりにも知能が高い為に周囲となじめず、誤解されやすい。
日本の「同調圧力」社会の中ではとても生きづらいそうです。
新聞記者である著者が当事者を取材し、『朝日新聞デジタル』の連載を書籍化。
正しく知ることは大切なことだと感じます。
【同調圧力】・・・集団での意思決定の際に、多数派の意見と同調させるように作用する暗黙の圧力。(『大辞林 第4版』より)
『愛という名の切り札』 谷川 直子//著 朝日新聞出版 F-タ
愛って、何だろう。
結婚って、何だろう。
14年連れ添った夫から、突然離婚を迫られ困惑するライターの梓、
専業主婦の百合子、非婚を選ぶ香奈、事実婚の理比人。
それぞれが愛に対して、真剣に向き合うハラハラドキドキの愛の物語です。
『ライオンのおやつ』 小川 糸//著 ポプラ社 F-オ
著者がお母さんのことをおもって書いた
「おなかにも心にもとびきり優しい、お粥みたいな物語」
読み終わったら
いまの生活を
人との出会いを
おやつの時間を
愛おしく、大切に感じるかもしれない・・・
『お探し物は図書室まで』 青山 美智子//著 ポプラ社 F-ア
20代から60代の、魅力ある人たちが主人公の、5つの短編集。
そこは、引き寄せられるように訪れた小さな図書室。
主人公たちは、司書の小町さんが発した「何をお探し?」の一言に、
心の中の想いを吐露してしまい…小町さんが選んだ、絶妙な本と付録に
勇気づけられ、前を向き直し、再び歩き出す!
主人公たちは、一体どんな答えを導き出したのか?
2021年 本屋大賞第2位。
話の続きが気になる、ワクワクしながら読める物語。
『成瀬は天下を取りに行く』 宮島 未奈//著 新潮社 F-ミ
【成瀬あかり】
きっと、この名前を忘れない
たぶん、どこかにいる気がする
どこにでもあるような日常
誰にでも起こりそうな出来事
だけど彼女が関わるだけで
忘れられないモノになる、コトになる・・・
そして、あなたは彼女に会いたくなる!!
『赤い手袋の奇跡 ~サラの歌~』 カレン キングズベリー//著 集英社 933-キ
年齢を重ねると、いろいろなことを諦めなければならないことが増えますが、
この本を読み「サラの歌」を詠んだ時、まだまだやれる!!という気持ちになりました。
何か悩んでいる時に読みたくなる一冊です。
『世界の家の窓から ~77カ国201人の人生ストーリー』 主婦の友社//編 主婦の友社 290.8
表紙には、窓の外から中を覗いたヤギ(?)の写真。そのとぼけた表情に魅かれて、
この本を手に取りました。
2020年3月、新型コロナウイルスの流行のため、各国で隔離政策やロックダウンが始まりました。
外へ出ることは許されず、窓からの景色を見るしかなくなってしまった人たちが、
「私の窓からの眺め」を写真に撮って、facebookに投稿したものが本になりました。
窓から見えるのは、ペットや野生の生き物、ご近所の洗濯物、庭や畑、そして、人が消えた街の様子。
窓の外に広がる景色と添えられたコメントから、遠い国の、顔を見たこともない人々の暮らしや
想いをうかがい知ることができます。
当たり前だった日常がそうでなくなった時、失ったものの大きさに気づかされます。
『旅の食卓』 池内 紀//著 亜紀書房 291
…ふらっと旅に出かけてみれば、きっとすてきな発見がある。
忘れられない人との、そして食との出会い。居酒屋料理からおやつまで、心に残る
「そこでしか食べられない味」を求め、今日も旅の達人・池内紀がゆく。
ゆったりのんびり旅気分にひたれる、大人のための散歩エッセイ。
亜紀書房の内容案内より
著者は姫路市生まれでドイツ学者でエッセイスト。この本に添えられた、味のある(?)
イラストもご本人によるものだとか。
そして合わせてご紹介したいのが、
『散歩本を散歩する』池内 紀//著 交通新聞社 915-イ
こちらも、散歩好きの著者がイラスト付きで街案内をしてくれます。
『ここだけのお金の使いかた』 アミの会//編 中央公論新社 F
アミの会とは、実力派女性作家集団。これまでにも既刊作品多数。
メンバー以外の作家がゲストとして参加することもあり、今回は原田ひ香さんが参加している。
本作は、ゲームの課金、給料、宝くじの当選金、子どもの教育費など、お金がテーマの短編集。
読後、自分がお金をかける対象って何だろうと考えてみた。
お金があれば幸せになるわけではないが、最低限のお金は必要か・・・。
『じゃむパンの日』 赤染 晶子//著 palmbooks 914-ア
幼い日や学生時代、大人になってからの日々の出来事や気付きを綴ったエッセイ。
作家の岸本佐知子さんとの交換日記も収録。
こだわりを持ちつつも、どこかゆるいところがおかしさを誘い、クスクス笑いが止まらない♪
楽しめる一冊です。
『彼女たちの山 ~平成の時代、女性はどう山を登ったか~』 柏 澄子//著 山と渓谷社 786
本書は、月刊誌『山と渓谷』2020年4月号から12月号まで掲載した内容に再取材のうえ、加筆修正しまとめたもの。
平成の時代、世界の山を愛し、登ることにこだわり続けた女性クライマー5人、
山野井妙子、田部井淳子、谷口けい、野口啓代、遠藤由加たちの話や、
山小屋、山岳ガイド、山岳部など山とかかわってきた女性登山者の話が収められています。
「本書を開いて、山に登る者たちの心のうちや行動の数々を、身近に感じてもらえたらうれしい。
私はみなから勇気をもらった。」と著者。
『忘れないでおくこと ~随筆集 あなたの暮らしを教えてください 2~』 暮らしの手帖編集部//編 暮らしの手帖社 914
雑誌『暮らしの手帖』に掲載された随筆の中から「日々の気付き」にまつわる作品を収録。
小説家、詩人、写真家、漫画家、ミュージシャン、俳優、格闘家など多彩な67人が
それぞれの忘れないでいる大切なことを綴ったエッセイが収められています。
1篇が3ページほどと短いので、少しの時間で読めるところもおすすめです。
『何げなくて恋しい記憶 ~随筆集 あなたの暮らしを教えてください 1』もあります。
こちらは「家族、友人、恩師」にまつわる作品を収録しています。
『あの夏の正解』 早見 和真//著 新潮社 783
2020年5月20日、全国高等学校野球選手権大会の中止が決定した。
今年の夏、4年ぶりに声援の戻った夏の甲子園で、慶應高校が107年ぶりの優勝を果たし幕を閉じた。
3年前、あの年の高校3年生は挑戦することもできずに夏が終わったのだ。
甲子園という目標を失った球児たちはあの夏をどう過ごしたのか、指導者は球児たちに何と言葉をかけるのが正解だったのか、そして球児たちは自分の未来のためにどう決着をつけたのか。元・高校球児で小説家の早見和真が「あの夏」を追いかける。
『図書館ウォーカー 旅のついでに図書館へ』 オラシオ//著 日外アソシエーツ 016
著者が旅のついでに巡った66の図書館を、旅行者目線で描いた、写真付きエッセイです。
訪れた町や図書館のとても美しい風景写真は、見ているとまるで、実際にその場にいるような気持ちになります。
あんな場所に、こんな図書館があったのか!と、ワクワクしながら読める1冊です。
『言の葉連想辞典』 遊泳舎//編 あわい//絵 遊泳舎 814
「日常を少しだけ豊かにしてくれる」という視点から選ばれた言葉が集められています。
それは、自然・感情・行動・場面・色などのテーマとなる漢字・文学から派生する言葉の数々。
風情のある表現から日本語の趣の深さを感じ、言葉の世界が広がります。
テーマをイメージしたイラストも素敵で、手元に置いておきたくなる一冊です。
『星落ちて、なお』 澤田 瞳子//著 文藝春秋 F-サ
2021年直木賞受賞作品。
江戸時代末期の絵師、河鍋暁斎(かわなべ きょうさい)とその娘とよを描いた物語です。
江戸、明治、大正と変わってゆく時代の中で、自らのスタイルを貫き、
自分が美しいと思うものを描き続けた暁斎。
また天才ともいわれ、あまりに大きな存在の父と向き合いながら、自分の生きた証を残す役目を見出していくとよ。
河鍋暁斎の画集とともに手に取ってみてください。
『二番目の悪者』 林 林子//著 小さい書房 726
あの有名人が言ってたから・・、友だちから聞いた話だから・・、ちまたで話題になっていたから・・、等々
うわさを信じる理由はたくさんあります(事実かどうか確かめもせず・・)。
この本の中で第三者として現れる雲の言葉、「噂は向こうから巧妙にやってくるが、真実は、
自らさがし求めなければ見つけられない」この文に心がざわつきました。
はたして「二番目」というのは誰のことなのでしょう?
『暮らしを変える書く力』一田 憲子//著 KADOKAWA 816
《言葉》をみつけるということは
わかったつもりだったのに実はわかっていないかったことに
輪郭をつけて、誰かに手渡すこと
そして、誰かの見つけた真実と交換し合うこと
新しい時代の文章レッスン 受けてみませんか
『くじけないで』柴田 トヨ//著 飛鳥新社 911.5
90歳を過ぎてから、詩を書き始めた著者のトヨさん。
日常生活や思い出を題材にしたベストセラー詩集です。
トヨさんの、年を重ねたからこそできる表現や言葉に、元気をもらえます。
おすすめは54ページの”くじけないで”。
トヨさんが感じた陽射しを、あなたにも届けたい。
『夏の体温』瀬尾 まいこ//著 双葉社 F-セ
著者が「友情をテーマに書こうと思って書き始めたわけではない」というのがよくわかる
なにげない日々のなかで、なにげないやりとりの中で始まる・・・うまれる《友情》
すぅ~っと爽やかな気持ちになる・・こころがポッとあたたかくなる・・
小学生の瑛介、中学生の明生、大学生の太原
それぞれの《ともだち》をえがいた全3編
『三つ編み』レティシア コロンバニ//著 早川書房 953-コ
生きている場所も年齢も全く違う女性の物語。
最後には思わずうなる展開に。
読後、力強く生きる勇気をもらえる小説。
『ニューヨークの女性の「強く美しく」生きる方法』エリカ//著 大和書房 159
幸せの基準を決めるのは、あなたです。
ニューヨークへ単身渡り、競争の激しい世界で一人、ビジネスを行う筆者。
そこで出会った素敵な人たちから学んだ習慣や美しい思考を紹介しています。
読み終えたとき、あなたはきっと、すがすがしい気持ちに包まれていることでしょう、と筆者。
『きみは太陽のようにきれいだよ』チェマ エラス//文 童話屋 726-エ
広場で開かれるパーティーに、ホセは妻のアナを誘います。
でも自分はもうおばあさんでパーティーには似合わないと言うアナ・・・。
ホセは「君は美しい!そのままでいい!」とやさしく言い続けますが・・・。
こんな老夫婦になるのが理想です。
とっても優しい気持ちにさせてくれる一冊です。
『美しい和菓子の図鑑』青木 直己//監修 二見書房 383
和菓子はお正月の花びら餅に始まり、春の桜餅、柏餅、夏には錦玉羹や葛饅頭、
秋になると、菊や紅葉などの練り切りをはじめ、栗きんとんや亥の子餅、年末には
歳神さまの依り代となる鏡餅、と一年中私たちを楽しませてくれます。
一つ一つの和菓子の解説や由来、昔ながらの和菓子の紹介もされています。
ホッと一息、和菓子とお茶で体も心も癒されてくださいね。
『おいしい暮らし 北インド編』有沢 小枝//著 教育評論社 292.5
東京麹町にあるインド料理の老舗アジャンタのオーナーである夫とともに、インド各地を訪ね、
食、歴史、文化について綴ったエッセイです。
日本でおなじみのあの野菜の期限がインドだとか、マスタードの花が咲き乱れる黄色い畑、
象の背に乗ってお城巡り、駱駝研究所の見学の話など、インドへの興味が深まる一冊です。
南インド編もありますので、さらにインドを知りたい方はぜひ!
『10代からのSDGs いま、わたしたちにできること』原 佐知子//著 大月書店 333
SDGsのゴールを目指すためにわたしたちに何ができるのか。
個人や団体による具体的な事例が紹介されており、こういう取り組み方もあるのだなと
知ることができます。「マゼンダ・スター」ってどんなもの?今は亡き中村哲医師、
ユニクロや劇団四季・・・、そしてセサミストリートが50年以上前の番組開始当初から
目指していたものとは?
「世界はたくさんの人とつながることで変えられる。
第一歩は、人の心に目を向けることから。」
『世界魔法道具の大図鑑』バッカラリオ・オリヴィエーリ//文 西村書店 902
マラクルーナ氏の魔法道具のコレクションがまとめられた一冊です。
あまり知られていない珍品から世にも名高い宝器まで、全部で210個。
例えば有名なところでは・・・ドロシーの銀の靴、ミス・ポピンズの傘、如意棒、
銀の椅子、おかゆの小鍋、人魚姫の飲み薬、魔女たちの箒、組み分け帽子、
ジャックのハープ、アウリン、ナルニア国の衣装だんす、賢者の石などなど。
それらが何の話に出てきた道具だったか思い出すのも楽しい!
この中でもし自分がもらえるならどれ?考えるだけでワクワクしてしまう。
『山小屋の灯』小林 百合子//著 山と渓谷社 291.5
全国の山小屋を訪ねた編集者と写真家によるフォトエッセイ集。
・・・煙突から上る細い煙が、ひっそりした森の中に人間の営みがあることを知らせているようで、
山小屋というのは山の中にあるからこそ魅力的なんだなあ・・・ 本文より
季節ごとに訪れたい山小屋が見つかります。
山小屋への憧れが募る一冊です。
『死ぬ瞬間の5つの後悔』ブロニー ウエア//著 新潮社 936-ウ
著者のブロニー・ウエアは緩和ケアの介護を長年つとめ、多くの患者を
看取った経験を基にして書いたブログが注目を集めました。
数多くの最後を看取ってきた彼女が患者の死の床で聞いた、誰にでも共通する後悔。
「もっとお金を儲ければよかったという人はいない」誰もがする後悔とは…。
様々な最期を迎える方々の様子からは、全ては自分が選択している事なんだなあと
改めて感じさせられます。
タイトルとは裏腹にポジティブな思考へ繋がる一冊となるかもしれません。
『日本に住んでる世界のひと』金井 真紀//文・絵 大和書房 334
生まれた場所を離れて日本で暮すスポーツ選手、宣教師、出稼ぎに来たひと、
難民として逃げてきたひとなど、来日の理由は様々。
どの人生にもキュンとなる部分があり、人間のドラマがある。
理不尽で最低で、絶望したくなる話は、歴史上にも現在にも、海外にも国内にもある。
この小さな世界の断片を一冊の本から垣間見た気がする。
『変な家』雨穴//著 飛鳥新社 F-ウ
YouTubeで話題の覆面作家・雨穴(うけつ)。
謎の空間、二重扉、窓のない子ども部屋-。
間取りの謎をたどった先に見た「真実」とは!?
2024年春、映画化決定!!
待望の第2作『変な絵』も合わせてどうぞ。
『波うちぎわのシアン』斉藤 倫//著 偕成社 91-サ
小さな島の診療所でフジ先生に拾われた少年シアン。
開かない左手に耳を近づけると、母のお腹にいた記憶を呼び覚ます力がありましたが、
自分は生まれたことに罪悪感を持っていました。
人は誰でも愛されて生まれてくることを、あらためて感じさせてくれる物語です。
『本当の「心の強さ」ってなんだろう?』齋藤 孝//著 誠文堂新光社 159
メンタルを強くするとは、感情に振り回されなくなること。
大事なのは、強度より柔軟性。柳のようにしなやかに、打たれ強い心があったなら。
野球界で話題の大谷翔平選手を、柔軟な身体と同じくらい、心も柔軟なように著者は感じるそうです。
著者自身や、著名な人々のエピソードも多く、勇気づけられる1冊。
『それでも旅に出るカフェ』近藤 史恵//著 双葉社 F-コ
カフェ・ルーズのメニューには、いろんな国のスイーツや飲み物が並んでいます。
それは、店主が世界各地を旅して、その地方で長く愛されてきた食べ物を教わり再現したもの。
季節のモノ、体に良いモノ、好みに合うモノなど、その時その人に合うモノを、店主が勧めてくれます。
訪れた人にとって、おなかだけでなく心も満たしてくれるカフェなのです。
本書は、旅に出るカフェシリーズの2作目。
1作目の『ときどき旅に出るカフェ』もあります。
『答えは市役所3階に』辻堂 ゆめ//著 光文社 F-ツ
コロナ禍の中、市役所に開設された「こころの相談室」が舞台。
相談者は全てを語るわけではない。切実な悩みと気づいてもらいたい想いとはうらはらに、
知られたくない秘密もあったりして…。
心理カウンセラーの晴川と正木が、相談者の悩みの相談にのりつつ、真実を推理する。
そして、実は、5人の相談者が繋がっているという連作短編集。
『人生の一冊の絵本』柳田 邦男//著 岩波書店 019
~絵本には、幼き日の感性の甦りや心の持ち方の転換がある~
大人になった今だからこそ読んでほしい絵本がこの本の中にたくさん紹介されています
是非〝あなたの一冊″を見つけてください
『グレゴワールと老書店主』マルク ロジェ//著 藤田 真利子//訳 東京創元社 953-ロ
本とは無縁だった青年グレゴワールが本に埋もれて暮らす老人と出会ったことから始まる物語
読書案内はそのまま人生への道案内でもあった!
青年の成長と老いの真実についても考えさせられる作品
『あたしの一生 猫のダルシーの贈り物』パディー レディー//著 江國 香織//訳 飛鳥新社 933-レ
読み始めたら止まらなくなる、猫好きにはたまらない本です。
猫を飼っている方は、きっと今以上にその猫が愛おしくて
たまらなくなるはずです。
『映画と旅する365日』パイインターナショナル 778
365日それぞれの日に合わせた映画とその舞台になった風景が素敵です。
自分の誕生日に紹介されている作品と場所がとても見たくなります。
春は出会い、夏はバカンス、秋はファンタジーやミステリー、冬はゆっくり
見たい名作やホラー等々。
『最後まで在宅おひとりさまで機嫌よく』上野 千鶴子//著 中央公論新社 367
桐島洋子、澤地久枝ら10人のロールモデルと人生後半の生き方を語り合います。
最後まで自宅の暮らしと「在宅ひとり死」を全うするために、何をしておくべきか
考えておかなければなりません。
1.人生100年時代、先輩方の覚悟
2.節目を超えてさらに輝く
3.老後は怖い?怖くない?
『ふるさと再発見の旅 東北』清永 安雄//撮影 産業編集センター 291
「日本の原風景に出逢う旅へ もう一度ニッポンをひもといてみませんか」
をコンセプトに出版された写真紀行シリーズです。
訪れたこともないのになぜか懐かしい気持ちになり、そこに暮らす人々の暮らしぶりが
感じられる写真が多数。
日本各地の記憶に残る風景や街並みが紹介されています。
最新刊の東北以外に、近畿①、近畿②、甲信越、中国地方、関東地方も所蔵しています。
まだ知らなかった日本を再発見する旅に出てみられませんか♪
『喫茶とまり木で待ち合わせ』沖田 円//著 実業之日本社 F-オ
喫茶店が舞台の短編集です。
なんの理由もなくても、何か理由があっても、誰でも少しだけ羽を休め、ゆっくり呼吸
ができる場所。どこにいたって息がしづらいと思っている人が、ほっとひと息ついて、
ゆっくり自分のことを考えられるような場所。
それが、「喫茶とまり木」。
じんわりと心が温まる話が収められた一冊です。
『小さな旅のフォト・スケッチ』丹野 清志//著 ナツメ社 291
観光地や絶景の写真ではなく、その土地の街や自然の匂いが感じられる写真が掲載されている。
街歩き旅を続けている著者が、四季のうつろいの中で出会ってきた街や自然や人々とのささやかな
出会いの記録集だそうだ。
「あなたの旅の記憶と重ね合わせて、一緒に旅する気分で読んでいただけたら…」と著者。
『病と障害と、傍らにあった本』斎藤 陽道ほか//著 里山社 019
病や障害のつらさは、心身の苦しみのみならず、固有な症状や想いを抱え、孤立してしまうこと。
そんな時、心を通わせた存在となった本はあったのか。
12人の当事者、介護者の読書体験が綴られたエッセイ集です。
生きることの困難に出会ったら、どうするでしょうか。
自分にとって支えとなり導いてくれる本を求め、探し続けたいものです。
『孫と私の小さな歴史』佐藤 愛子//著 文藝春秋 914-サ
百寿を迎え、現在も雑誌『婦人公論』での連載を執筆されている佐藤愛子さん。
1991年生まれの孫・桃子さんと20年間、毎度ヘトヘトになりながら、年賀状の写真を
撮り続けたそうです。桃子さんが成長するにつれて、どんどんテーマが壮大に。
こだわりを感じる写真の数々にクスっとなります。
「祖母はいつも仕事第一で、私を気遣ってくれることなどめったにありません。
年賀状撮影も私にすれば、ひたすらくだらない、面倒くさいことでした。
でも、祖母がやると言えば、とにかく腹をくくって付き合うしかないのでした。」という
桃子さんの言葉から、エネルギーに満ち溢れ全力で楽しんでおたおばあちゃん
(佐藤愛子さん的には、じいさん?)の姿を想像します。
『ジジイの片付け』沢野 ひとし//著 集英社 597
……片付けを習慣にすると、健康、安心、老後の喜びといいことずくめである。
思い立った時に片付けるのではなく、ジジイは今後のならわしを片付け中心にして、
そして片付けを趣味にして欲しい。ただし、家族の者に嫌われないために、物音をたてず、
大声をあげず、静かに専念すること。
生き抜くためには片付け、これしかない。 著者あとがきより
と、モノに縛られない暮らしへの方向転換のススメが書かれてある。
『ジジイの台所』沢野 ひとし//著 集英社 596
「おいしいものが生まれる場所には、いつも笑顔がある。
台所はジジイにとって、また家族にとって、すべてのはじまりである。」
と、まえがきにある。
本作は『ジジイの片付け』の第二弾。
料理の本ではなく、あくまで台所が主役の本だとか。
とは言え、簡単、ヘルシー、経済的なレシピも載っているのが嬉しい。
『偶然の散歩』森田 真生//著 ミシマ社 914-モ
タイトルの「散歩」とは、幼い子どもたちとの本当の散歩や、哲学者や思想家との時空を超えた思索の散歩のこと。
数学者である著者は言う。
散歩はあらゆる生き物との遭遇の場である。世界は広くて狭い、さまざまなものが繋がっていてその中で生かされていると。
一度きりの偶然の向こうに、いつまでも残り続ける何かを見ている。
一度きりと永遠は、どうしてこんなに似ているのだろうか…と。
この本のことを上手く伝えられませんが、読後はスッキリ!
自分の視野が広がった気がしました。
『3人で親になってみた~ママとパパ、ときどきゴンちゃん~』杉山 文野//著 毎日新聞出版 916-ス
トランスジェンダーである著者は、フェンシング元女子日本代表。
3人で親になる。パパ、ママ、そして…
著者がパートナーの女性と、ゴンちゃんと、子育てに奮闘する日々を綴ったエッセイです。
LGBTQの方が子どもを授かり、新しい形の家族を築くということ、そこには葛藤もあるが
一つ一つの問題や壁、心配事に向き合っていく姿が勇ましくて温かい。
夫婦の在り方、育児の考え方についても学びがあり考えさせられました。
『52ヘルツのクジラたち』町田 そのこ//著 中央公論新社 F-マ
52ヘルツのクジラ。仲間とは声の高さ-周波数が全く違うため、他のクジラにはその声は聞こえない。
世界で一番孤独なクジラ。
自らの人生を家族に搾取され続けてきた女性・貴瑚と、母に虐待され「ムシ」と呼ばれていた少年。
どうか彼らの声が誰かに届きますように。優しく受け止めてもらえますように。
2021年本屋大賞受賞。
『あなたのための短歌集』木下 龍也//著 ナナロク社 911.1
依頼者からメールで届くお題をもとに短歌をつくり、封書にして届ける…という、
短歌の個人販売によって生まれた短歌たち。
本来ならこうして公開されることはなかった、たった1人の「あなたのため」につくられた短歌たち。
でも、あなた以外の「あなた」のためにつくられたのでは?と思えるような1首に出会えるかもしれません。
※最後のページまでめくるのをお忘れなく!
『素晴らしきお菓子缶の世界』田中 ぷう//著 光文社 675
身近にあふれるお菓子の缶。
お家で小物入れになっている親しみのあるものから、いつかは手に入れたいあこがれのものまで。
ながめるだけで幸せな気分になります。
『フーテンのマハ』原田 マハ//著 集英社 915-ハ
旅好きマハさん。マハさんの半生もよくわかる一冊。
笑いあり、感動ありの取材旅行エッセイ本。
食・陶器・絵画・鉄道を求めて、日本中、世界中をとび回る!!
マハさんと一緒に出かけ、旅した気分!
『この道の先に、いつもの赤毛』アン タイラー//著 早川書房 933-タ
主人公のマイカは、43歳ひとり暮らし。アパートの管理人兼コンピューターの便利屋をしている。
毎朝、ランニング→シャワー→朝食→掃除のルーティーンを崩さない。
つき合っている彼女はいるが、結婚する気はない。
変わらない日常が続くのかと思われるが、ある日、自分の息子を名乗る青年が現れ事態は一変する。
このまま今まで通りの日々を過ごしたいのか、そうでないのか…。
マイカは、自分の中のホントの気持ちに気づき、いつもと違う「ちょっとしたこと」を
試してみる。と、そこには新たな展開が…。
『聡乃学習』小林 聡美//著 幻冬舎 914-コ
著者は、俳優の小林聡美さん。
50歳を前にスタート、5年にわたって書き続けたエッセイが本になりました。
…今やりたいことは、今やっておかなくては。
身体の衰えを感じつつ、時代の流れを感じつつ、それでも見聞を広め知識を吸収する。
淡々と前向きに、マイペースでいいから。…と言いつつも、結構パワフル。
なかなか自分にはできそうもないけれど、
「トライアル アンド エラー」という言葉は、おまじないのようで心強い。
『解きたくなる数学』佐藤 雅彦・大島 遼・廣瀬 隼也//著 岩波書店 410
数学に苦手意識のある方、多いのでは?(私も…)
思わず目を背けたくなる暗号のような問題…
でも、それが不思議と「解きたくなる」のです!
NHK教育テレビ「ピタゴラスイッチ」を手がける3人だからこそ成せるワザ。
考えるのが楽しくなる1冊です。
『I love letter』あさの あつこ//著 文藝春秋 F-ア
主人公の岳彦17歳は、この半年近くほとんど部屋から出なかった元引きこもり。
ひょんなことから、会員制の文通会社で働き始めた。
「まめに手紙をくれてた人が急に音信不通になるって、どんな場合?」
それぞれに書けない理由、それぞれの書かない理由があったりして…
タイトルから、甘い話を想像していたらどんでもなかった。
これは、サスペンス!
手紙には、メールや電話では伝わらない想いが込められている。
『世界のひきこもり』ぼそっと池井多//著 寿郎社 367
先進国に限らず貧しい国にも、ひきこもりは世界中にいるらしい。
各国で生活するなかで、どんな事がきっかけでひきこもりとなったのか、
どのような生活をしているのか?ひきこもりを脱しようとしている人、
ひきこもりであることを受け容れている人…と多様である。
ひきこもり歴35年、「世界ひきこもり機構」を設立(2017年)した50代の著者が、
インターネットを介して海外のひきこもり当事者と対話し、「ひきこもり」は
日本特有の現象でないことを提示しています。
『ごきげんな散歩道』森沢 明夫//著 春陽堂書店 914-モ
これまでに著者の小説をいくつか読んで、とても繊細な表現をされる方だなぁと感じていました。
この本を読んで著者の人となりを知ることができて、満たされた気持ちになりました。
散歩に出て、空を見上げて足元にも目を凝らして…やさしく面白い視点やロマンを感じる発想、
あたたかい言葉が詰まっています。
『パリのすてきなおじさん』金井 真紀//文と絵 広岡 裕児//案内 柏書房 361
パリの街で出会ったおじさんたちのインタビュー集。
個性豊かな似顔絵も添えられている。
年代、職業も様々。人種、宗教などそれぞれの背景を背負いながらも、パリの生活を大切に
しているおじさんたちの言葉は、意味深い!
「世界は想像以上に込み入っている。」とは、著者の言葉。
『アルプスでこぼこ合唱団』長坂 道子//著 KADOKAWA 916-ナ
スイス在住20年の著者だが、なかなか周囲になじめない。それは、アンフレンドリーな
スイス人の国民性か、スイスドイツ語の言葉の壁のせいなのか…。
ひょんなことから、地元の合唱団に加わるが、メンバーの国籍も様々、職業や趣味もわからず、
話すきっかけすら見つけられない。
さらに、コロナ禍のため練習はリモート!!
「いろいろあった4年間は、私にとって、みんなと声を合わせて歌う時間であると同時に、
スイスへのゆっくりテンポの同化の時期。この地での居場所探しの時間でもあった。」と、著者は書いている。
人と仲良くなるには、アダージョのテンポで、気長に根気よくってことかな~。
『明日咲く言葉の種をまこう』岡崎 武志//著 春陽堂書店 159
本(小説・エッセイ・詩・漫画)から映画、ドラマ、墓碑銘まで、
著者が書き留めたものの中から、とっておきの名言を紹介。
名言が生まれた背景やエピソードも綴られています。
巻末には「引用作品一覧」があるので、お気に入りの名言に出会えたら、
元の作品を読んでみるのもいいかもしれません、
『MINIATURE LIFE at HOME』田中 達也//写真・編集 水曜社 748
よくあるお家でのワンシーン…?
よく見ると…なるほど!!
NHK連続テレビ小説「ひよっこ」のオープニング映像を手がけた、
ミニチュア作家・見立て作家である田中達也さんの写真集です。
『11の秘密』アミの会(仮)//編 ポプラ社 F
著者の、アミの会(仮)とは、 一応女性だけの書き手の集まり、話し合いでテーマを決めて競作し、
書き下ろしのアンソロジーを刊行するグループ。(あとがきより)
今回は、11人の作家さんによる短編集です。
テーマは、「ラスト・メッセージ」。
記されたメッセージの秘密を探る「謎解きの宝箱」みたいな1冊です。
『心に輝く旅の宝石箱』交通新聞社 914
この本は、JR西日本が発行する広報誌『Blue Signal』に収められた旅のエッセイ集です。
著者は、作家、作曲家、映画監督、落語家、バレリーナ、棋士、騎手など。
それぞれの旅の思い出の数々が綴られています。
思うようにお出かけできない今、忘れられない「あの場所」はどんなだろう…。
いつか再び訪れる時まで、どうか変わらずそのままであってほしい。
そして、そのいつかが早く来てほしいと願っている。
『中学生の頭の中身をのぞいたら、未来が明るくなりました。』なりたい大人研究所//編 KTC中央出版 816
「将来、あなたはどんな大人になれたら幸せですか?」
この本は、第1回「なりたい大人作文コンクール」(2019年)に
寄せられた作品で構成されているそうです。
中学生のまっすぐで、純粋な言葉。可能性は無限大。
大人が思っている以上に、身近な大人をみて、多くのことを
感じていそうです。大人の方にも読んでもらいたい。
「あなたは、どんな大人でいられたら幸せですか?」